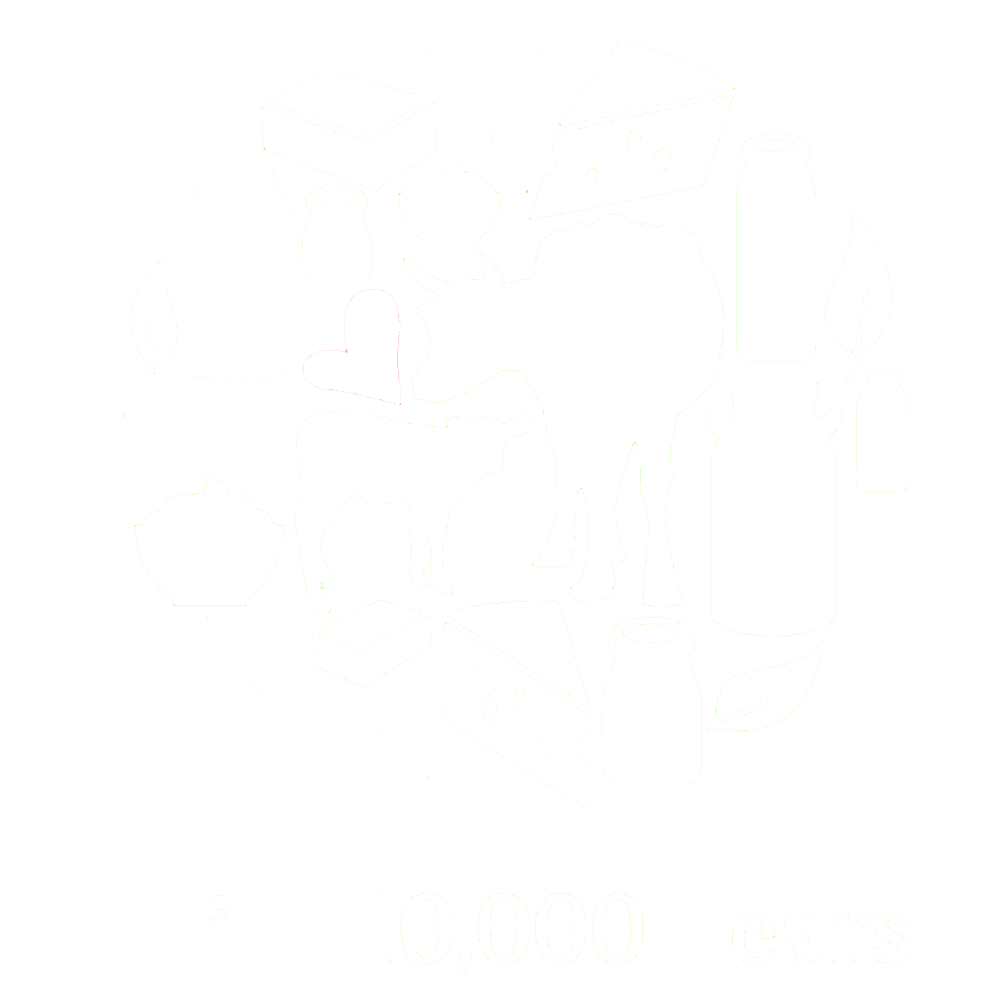ミルク1万年の会 ミルクで繋がる交流の集い2025~地域酪農の価値を共創する乳業の取り組み~
|
講演1 株式会社岩泉ホールディングス 社長 山下欽也 氏 岩泉町は、東京23区と横浜市を足したほどの広大な面積を持つが、交通アクセスは決して良好とは言えず、町外からのアクセスも容易ではない。そうした中で、同社は物流・商品戦略・販売方法を工夫し、全国に日配品を届ける体制を築いた。 山下社長は元JA職員で、農協時代に築いた地域の酪農家との信頼関係を背景に、2009年に岩泉乳業の社長に就任。当初、同社は3億円の赤字を抱えており、非常に厳しい経営状況からのスタートだった。しかし、「この地域の生乳を活かし、価値ある商品をつくる」ことを信念に、牛乳からヨーグルトへと主力商品を転換。無添加で2日かけて製造する「岩泉ヨーグルト」は、他社が真似できない高付加価値商品として成長を遂げた。 同社の販売戦略は、「スーパーに頼らない」ことが特徴。ホテル・温浴施設・病院・宅配業者・通販・学校など、地道に行商や試食販売を続けながら販路を拡大していった。特にドリンクヨーグルトとアルミパウチタイプのヨーグルトはヒット商品となり、現在ではドリンクヨーグルトは1日約4トン、アルミパウチは年間約4300トン製造されている。宅配業者との提携により、遠隔地にも安定的に商品供給ができるようになり、全国各地でファンを増やしている。また、「岩泉乳業応援隊」というファンコミュニティを形成し、SNSを活用した情報発信や、工場祭の開催(全国から6000人が来場)などでブランドの浸透を図っている。 メディア戦略にも積極的で、大谷翔平選手や著名人が商品を愛用しているエピソードを活用し、テレビ・ラジオ・新聞などで広く広報活動を行っている。また、商品パッケージには顧客の声をQRコードで読み取れるようにし、リアルな評価や感想をダイレクトに届ける工夫もしている。 岩泉ヨーグルトを軸に、商品展開も多角化。炭酸水、サイダー、化粧水、ラーメンとのコラボなど、地元産品と融合した企画が多く、岩泉ブランドをより広げる工夫がなされている。社員旅行を兼ねたモンドセレクション受賞式参加など、社員のモチベーションアップにも力を入れている。さらに、女子サッカーチームのスポンサーや、全国のマラソン大会への協賛などを通じ、地域外でも「岩泉」の名を広げる取り組みをしている。岩泉乳業のスローガンは「小さな市場でクジラになる」――大手企業が手を出さないような狭く深い市場で、強いブランドを築き上げることを目指している。 また、ジェラート事業も展開しており、現在は盛岡と花巻で直営店を運営。高知県や宮古島などでのフランチャイズ展開も計画している。ジェラートを通じて、地域農産物の活用や観光との連携も進めている。 労働力不足の課題に対しては、スリランカにある日本語学校と提携し、現地にマンゴー農園を設置。そこでの雇用支援を通じて、人的ネットワークと物的輸入の両方を確保している。スリランカで収穫されたマンゴーは、岩泉のジェラートやドリンクに使用され、国際連携型の地域資源活用モデルとなっている。 地元の酪農家との関係も大切にしており、設備導入の資金支援や、乳価上昇・飼料高騰時には1酪農家当たり10万円の特別支援金を支給するなど、生産者と二人三脚で地域酪農を支えている。生乳をそのまま出荷するのではなく、加工・製品化して販売することで、7億円分の原料乳が約25億円の売上へと変換され、地域経済に還元されている。 「岩泉の酪農を守り、次世代につなぐ」ことを使命とする山下社長は、商品づくりを通じて地域ブランドを育て、町に仕事と誇りを生み出している。「魅力ある製品が魅力ある地域をつくる」と語る山下社長の言葉には、地方の未来を自ら切り拓く強い意志がこもっている。 このように岩泉ホールディングスは、単なる乳業メーカーにとどまらず、地域を活性化し、持続可能な産業モデルを実現するためのロールモデルとして注目されている。 前のページに戻る 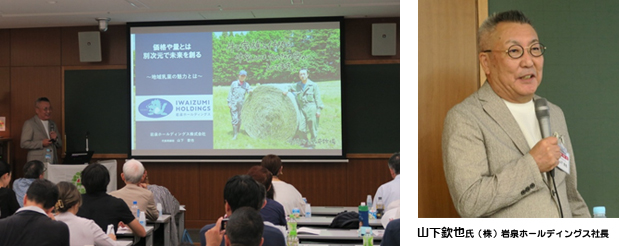 |