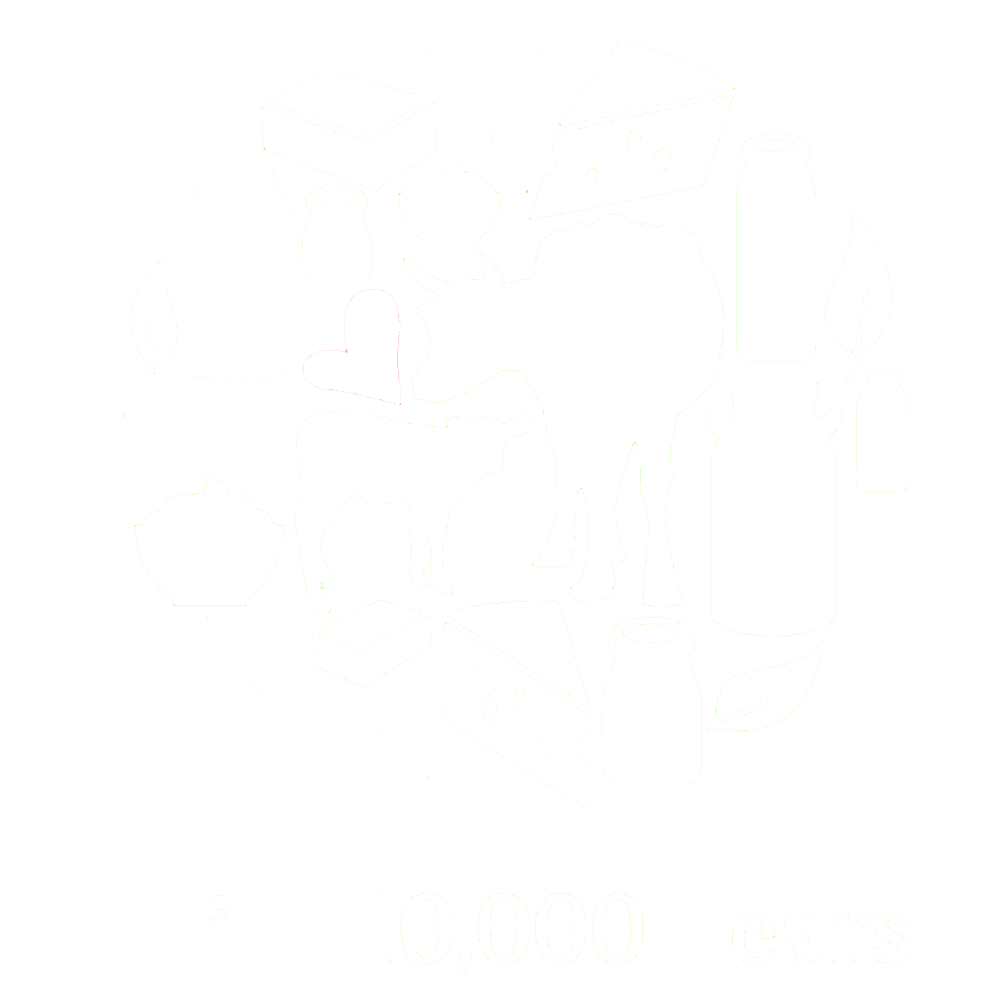ミルク1万年の会 ミルクで繋がる交流の集い2025~地域酪農の価値を共創する乳業の取り組み~
|
講演2 ひまわり乳業株式会社 社長 吉澤文治郎 氏 歴史と創業背景 創業は1922年(大正11年)。銀行員だった祖父が、仕事先の銀行が破綻し、その後、妹の体調改善のため山羊ミルクを与えた経験から牛乳の製造を決意。牛・ヤギを飼いビン詰めして配る形でスタートした。戦後、法人化し「土佐乳業」から「高知牛乳食品株式会社」を経て、やがて「ひまわり乳業」と社名変更。地元では「美味しくて濃い」濃縮牛乳「ひまわり牛乳」で人気を博した。 自身の経歴と地域との関わり 吉澤氏は東京の大学を卒業後、岡山大学で畜産物利用学を学んだ。その後地元に戻り、営業・企画を経て社長に就任。ずっと地元の歴史や文化を学び、ブログ「今日のにっこりひまわり」を22年間毎日更新。2016年にはNHK「ブラタモリ」高知編の案内人も務め、高知愛を深め地域と共に歩む姿勢を示している。 経営の指針:自然・健康・地域 高知はかつて本州から隔絶され物流が困難だったため、地域内だけで経済が回っていた。しかし交通網が整備されるとともに外部資本や廉価な商品が流入。激変する環境の中、ひまわり乳業は「自然・健康・地域」を三つの柱に据え、合致しない商品は作らないという方針を確立した。 差別化戦略と商品開発の実例 「他社と同じことでは勝てない、自社だからできる商品を開発する」という方針のもと、高知産すだち使用のヨーグルトシリーズ(ゆず・青汁風味)などを開発。手間とコストをかけて、食品デザインやブランドイメージで差別化を図った。国内初の宇宙ヨーグルト、牛乳にとろみをつけた商品、青汁「菜食健美」、ストローレス紙パック牛乳など、他社が真似できないユニークな試みを次々と行っている。 生産者との強い関係性 酪農家との密接な関係が基盤となり、商品の付加価値化を可能にしている。例えば「低温殺菌牛乳」は、搾乳日を明示することで鮮度を訴求、関西・関東にも最短で翌日配送。生産者の顔が見える関係、夜中の集乳など、現場との強い信頼関係がビジネスモデルを支えている。 同様に青汁「菜食健美」は、高知県大豊町の契約農家と連携し、契約・栽培・集荷・商品化を一貫で行う独自体制で生産。他社には難しいサプライチェーン構築を成し遂げている。こうした生産者との信頼関係こそ、ひまわり乳業の最大の資産である。 地域社会との連携と社会的意義 高知県の行政・JA・畜産部門などとも密にコミュニケーションを取り、乳質改善や価格交渉に関わる取り組みも展開。酪農家への奨励金支給や技術支援などを実施し、地域一体での酪農基盤の維持に貢献。地元の酪農家による乳質コンテストや飲み会交流など、距離を超えた関係性づくりを続けてきた。 具体的事例の紹介 ・とろみひまわりミルク:誤嚥性肺炎のリスクに対応し、病院以外でも家庭で使えるとろみ付き牛乳として開発。高齢者介護市場にも対応した革新的商品。 ・ストローレス紙パック牛乳:2021年より、学校給食用ストロー不要パックを導入し全国で約30%に普及。行政・教育委とも連携し普及を推進。 ・菜食健美青汁:契約栽培や農協支援により無農薬野菜を原料とし、90cc瓶で宅配専用商品として生産。独自ルートを活かした品質とブランドで関西・関東・九州にも展開。 今後の展望 高知という地域に根差し、生産者や行政と密に関わりながら他社ができないことを仕掛け続けることが、今後の差別化戦略。量産・低価格を求めず、特殊な付加価値(鮮度・機能・ストーリー)を追求する姿勢が中心である。現在は牛乳と青汁の二本柱でさらなる認知拡大を目指し、地域ブランドとしての地位を高めている。 前のページに戻る  |