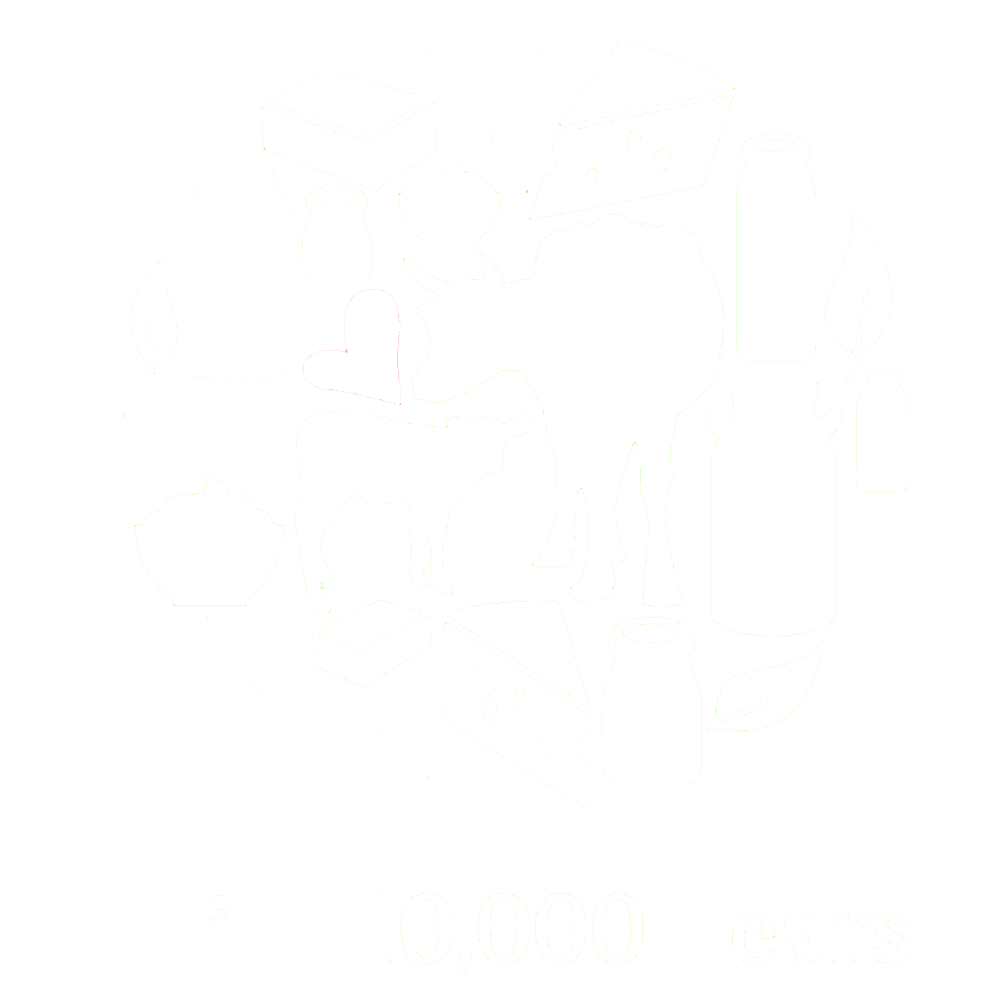ミルク1万年の会 ミルクで繋がる交流の集い2025~地域酪農の価値を共創する乳業の取り組み~
|
第2部 ディスカッション ディスカッションの背景と目的(前田氏よりの提起) 本セッションは、地域に根差した乳業・酪農の協働がどのように価値を創出し、地域社会と持続的に関係性を築いていけるかを議論するものである。ポイントは以下の4点。 ・地域社会や地域酪農の現状と展望 ・地域における酪農の価値とは何か ・酪農の価値を支える乳業・商品・サービスの役割 ・酪農と乳業、そして多様なステークホルダーとの連携・協働の課題  ディスカッションの要約 ~地域酪農の価値と乳業の役割を問う~ 岩泉町と高知県から見える課題と展望 2020年代に入り、農地の担い手不足と過疎化の進行が深刻さを増している。2024年6月の日本農業新聞によれば、10年後には全国の農地の6割が耕作放棄地になるという予測も出されており、特に岩手県・高知県といった人口減少率の高い地域ではその影響が大きい。今回のディスカッションでは、そうした地域における酪農の役割、乳業の責任、そして今後の連携と課題について、岩泉乳業(山下氏)とひまわり乳業(吉澤氏)両社の経験を通して考察した。 岩泉と高知に共通する現実:酪農家の激減 岩泉町では、1961年に1,155戸いた酪農家が、2015年には54戸、現在では20数戸まで減少。一方、高知県でも同年に1,757戸あった酪農家が、2015年には68戸、現在は30戸以下にまで落ち込んでいる。町単位の岩泉と県全体の高知で酪農家数がほぼ同等という事実は、それぞれの地域で酪農の位置づけが大きく異なることを示している。 岩泉では酪農は一大産業として地域の経済を牽引してきたのに対し、高知では酪農は主要産業とはみなされず、園芸などが中心であった。ゆえに、岩泉では住民の酪農に対する関心や関与が高い一方で、高知では県民の多くが酪農の存在すら知らないという温度差がある。 酪農の魅力と困難 山下氏(岩泉乳業)は、自身がJA職員時代に酪農担当が「エリート」扱いされていたことを紹介した。かつて酪農は岩泉町の中心産業であり、JA職員にとっても誇り高い部門だったという。しかし現在では、後継者不足と労働環境の厳しさから、若者が酪農に魅力を感じない状況が続いている。ヘルパー制度も機能せず、高齢化が進行し続けている。 吉澤氏(ひまわり乳業)も同様に、高知県では酪農の経営基盤は厳しく、メガ牧場などの規模拡大によってかろうじて支えられている状況を報告。後継者のいる50代の中堅酪農家への期待はあるものの、コロナ禍を経て廃業する事例も増えている。特に県民の酪農への理解と支援が乏しい点は大きな課題であるとした。 地域にとっての酪農の価値 岩泉町では、酪農は単なる産業ではなく、地域社会そのものを支える存在と見なされている。山下氏は、町民の酪農への共感や支援が高まった要因として、①町主催の酪農イベント、②地元ラジオでの情報発信、③岩泉乳業の雇用創出、の3点を挙げた。特にラジオは広い町内でのコミュニケーション手段として有効に機能し、住民の関心を喚起したという。また、岩泉乳業が地域の大企業として300人近い雇用を生み出していることも大きい。企業が地域の誇りとなり、酪農と乳業の両輪で町を支えているという認識が住民の中に共有されつつある。 一方、高知県では酪農の存在感は薄いが、ひまわり乳業では県内の酪農家の名前を記した「高知の牛乳」や、特定農家の写真入り「鹿島さんの低温殺菌牛乳」など、地域とのつながりを深める商品開発に取り組んでいる。これらは生産者の顔が見える取り組みであり、県民に酪農の存在を可視化し、共感を得る試みである。 酪農・乳業の連携と持続のための課題 山下氏は、岩泉乳業が今後も安定した規模を保ち、地域とともに歩むことを重視していると述べた。ヨーグルトの生産量を「1日12トン」に制限し、それ以上は生産しない方針を示した点は注目される。無理な拡大をせず、ブランド価値と品質を守る姿勢である。これは「拡大ありき」の一般的な企業論理に対する対抗軸とも言える。 また、今後の経営継承については、4人の執行役候補を立て、社内教育を重視していると述べた。酪農家との関係性を「利益還元の対象」として捉え、単に収益を追求するのではなく、地域・生産者・従業員との共存を大切にする経営哲学を強調した。 吉澤氏も同様に、酪農家との関係性が会社の基盤であることを認識し、それを若手社員に伝える努力をしていると述べた。特に若手社員が酪農家と直接交流し、生の声を聞く場を設けており、それが乳業に携わる意義を深く理解する機会になっている。 距離の課題については、高知県内の酪農家が点在していることから、1牧場の集乳に2時間かかることもあるが、会合や交流機会を重ねることで心理的な距離は近く保たれているという。 結論~地域を支える酪農・乳業の未来に向けて~ 今回の議論から浮かび上がるのは、酪農が単なる一次産業ではなく、地域社会の生業・文化・誇り・人のつながりと密接に結びついているという実態である。人口減少や高齢化が進行する中で、酪農の衰退は地域社会の基盤を揺るがす問題であり、乳業はその維持と再生のキープレイヤーである。 岩泉町では、企業と住民が一体となって酪農を支え、高知では商品を通して酪農の価値を可視化している。いずれも、地域と乳業が相互依存しながら生き残りをかけた挑戦を続けている。 経営者の哲学、地元住民の関心、そして次世代へのバトン――それらをいかに繋ぎ続けられるかが、地域酪農の未来を左右する。酪農と乳業の連携が、単なる原料と製品の関係にとどまらず、地域全体の持続性に貢献するものであることが、今回のディスカッションを通じて明確に示された。 会場との質疑 モデレーターの前田氏は、まずは2名を指名し発言を依頼した。 ひとりはM乳業のK氏。彼女は、大手乳業メーカーにおける酪農家との距離の遠さに課題意識を抱き、酪農家の6次産業化製品を集めて販売する新規事業を立ち上げた経緯を紹介。自身が農業志望だったことから、「乳業メーカーの中から生産者との距離を縮めたい」との想いで起案したと語った。 もうひとりは、酪農家・Y氏。彼は、全国の酪農家の急激な減少や、関東でも仲間が辞めていく現実を紹介した上で、「多くの酪農家に今日のような支援の声を届けたい」と訴えた。「支援はない」「選別されている」という諦めに近い空気の中にある酪農家に対し、実際には応援してくれる人が多くいることを知ってほしいと強調した。 その後、H大学の学生・N氏からは「後継者の育成において、教える側の育成も必要なのではないか」との問いがあり、岩泉ホールディングスの山下社長が応答。山下氏は、「不安を取り除くことが重要」と述べ、流通の整理や100%買い取る体制の整備、自分のミルクが何になるのかという情報提供の重要性に触れた。また、吉澤社長(ひまわり乳業)は「酪農家に自信を持ってもらうことが重要」とした上で、酪農家の奥様同士の情報交換など、横のつながりがスキル向上や意識改革に繋がっていると指摘した。 T乳業のN氏からは、山下氏に「事業継承時のモチベーション」および「多角化戦略の背景と相乗効果」について質問があった。山下氏は、地元岩泉への強い思い入れと、「逃げてはいけない」という覚悟から事業を引き受けたことを語った。経験がなくともやれることをすべてやるという姿勢で、土日の試食会など地道な努力を重ねてきたと述懐した。 また、多角経営については、地域の経済的つながりや信頼をもとに「紹介と縁で新しい事業が展開している」と説明。取引先との直結や連携により、地元の観光、食品、農産品などが統合的に発展していると述べた。新たな子会社化の可能性にも触れ、3年間の黒字を条件に受け入れる考えを示した。 O乳業のS氏からは「酪農家との関係性を築くうえで大切にしていること」を吉澤社長に質問。吉澤氏は、若い頃から高知の宴会文化や“返杯”を通じて築かれた酪農家との関係性を語り、「深く考えたことはないが、関係性だけは絶やさないことを徹底している」と語った。関係性は社風として若手にも継承しており、「最優先事項」として扱っているという。 元高知在住で岩泉とも縁のあるI氏からは、両地域の酪農文化の違いや、山地酪農・斎藤牧場とひまわり乳業の連携の仕組みについて質問が出された。吉澤氏は、斎藤牧場との取り組みは自然発生的なものであり、「弊社が小ロットの殺菌充填をできるから請けた」というシンプルな経緯を説明。配達に関しては、「山地酪農を愛する会」が基盤となり、弊社と販売店が補完していると答えた。 最後に、YミルクのO氏から「エコフィードのような農家や酪農家を横断する連携の可能性」について質問があり、吉澤氏は、青汁原料やコーヒー粕を堆肥に活用する例を紹介。コーヒーを使った牛ふん堆肥が高知新聞に取り上げられ、消費者の関心も高かったことを示した。 山下氏も、地元の畑わさび生産者が酪農家の堆肥を活用しており、地域内循環が機能していることを強調。また、しいたけ廃材(ほだ木)を活用した新たな事業も進行中で、1年以内に公表する予定だと語った。 前田氏は、まとめとして、「この2つの地域に共通するのは“酪農家が孤立していない”ことだ」と述べ、地元乳業の商品に対して酪農家が「自分たちの商品」として誇りを持てる環境がある点を指摘。乳業メーカーの商品が、生産者と消費者のコミュニケーション媒体にもなりうるという意義を再確認し、ディスカッションを締めくくった。 前のページに戻る  |